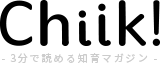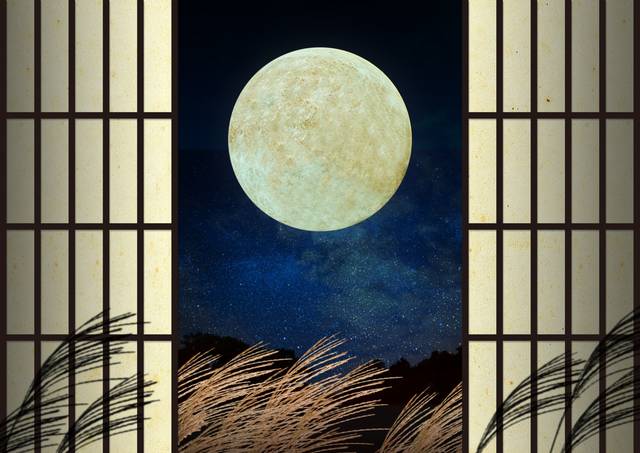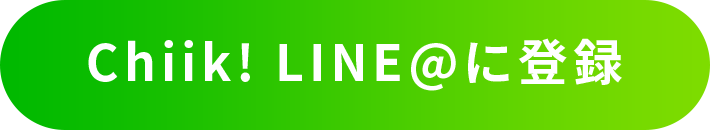中秋の名月、お月見は今でも日本人に大切な風習ですね。でもその由来やお団子・ススキなどをお供えする理由をご存知でしょうか?ここではお月見についてご紹介します。お子さまと一緒にお月見について知り、素敵な月を眺めましょう。
秋の行事として最初に思いつくのは「お月見」=「中秋の名月」ではないでしょうか。幼稚園や保育園の行事でお月見団子やススキや秋の花を飾ったり、お月さまの歌を口ずさんだり、子どもの頃の楽しい思い出が蘇ってくるかもしれません。
今回の記事では、お月見の由来や準備のアイディアをご紹介します。
日本の大切な風習でもあるお月見の行事、ぜひお子さまと一緒に楽しんでみませんか。
お月見・月がテーマの絵本|秋の夜長に子どもに読み聞かせたい10冊
お月見をする日(中秋の名月)はいつ?
お月見(十五夜)とは旧暦の8月15日、一年で最も月が美しいと言われる「中秋の名月」に月を鑑賞する行事です。この日の月は「十五夜」「芋名月」とも呼ばれます。
毎年「中秋の名月」の月日は変わります。10月上旬になることが多いですが、9月中のこともありますよ。
ちなみにお月見といえば「十五夜」のイメージが強いですが、実は十五夜以外のお月見の日も存在するんです。「十三夜」など他のお月見の日も合わせて調べて楽しんでみるのもいいですね。
▼他のお月見の日について気になる方はこちら
お月見の由来は?どうして始まったの?
お月見はもともと上流階級の人々が中秋の名月を楽しむ宴を催す雅な遊びでしたが、次第に農民たちの収穫祭と結びつきました。月の満ち欠けは農業や生活に深く関わっていて、満月に豊作の祈願と収穫の感謝をします。
またそれだけではなく、これまで命をつないでくださったご先祖さまを偲ぶ日でもあります。
お月見はもともと中国から伝わったという説もあります。
お月さまへのお供えの準備をしましょう
お月見にはお団子やススキが欠かせませんが、どうしてなのでしょう?正しいお供えの仕方があるのでしょうか。
◼︎月見だんご
月見だんごは十五夜にちなんで一寸五分(約4.5cm)のだんごを15個お供えします。真ん丸ではなく、少しつぶした形にします。真ん丸のだんごは死者にお供えするだんごと同じ形になってしまうためです。だんごの数は、省略して5個にする場合や一年の満月の数12個にする場合などもあります。15個の場合は下から9個、4個、2個の順に並べ、一番上の2個は正面から見て縦方向に並ぶように置いてください。だんごは先に食べてしまうのではなく、お供えしてからそれをお下がりとしていただいてください。
◼︎ススキ
作物の成長や子孫の繁栄を見守ってくださる月の神様への「依り代」と考えられています。本来は稲穂をお供えしたいのですが、この時期まだ稲穂は収穫できないため、見た目の似ているススキをお供えするとも言われています。
このほかに、果物やサトイモなどの野菜もお供えします。
月見だんごやススキはお月さまから見える場所か床の間に置きます。お月さまから見て左側にススキや収穫した野菜、右側に月見団子を供えるのが良いとされています。
▼お月見の工作にもピッタリ!うさぎの折り紙の記事はこちら
お月見の風習「おつきみどろぼう」
▼お月見どろぼうについてもっと知りたい方はこちら
日本以外の国でもお月見をするの?
中国では旧暦の8月15日を「仲秋節」とよび、「春節」(旧正月)に次ぐ大きな行事としてお月見がされています。サトイモなど秋の収穫に感謝し、月に拝みます。中に餡や栗、胡桃や卵黄などを入れて丸く焼き上げる「月餅」という伝統菓子を食べ、甘酒を飲む習慣があります。「仲秋節」には遠方にいる家族も集まり、皆で食後に月餅を食べて家族の幸せを願うそうです。
また台湾や香港でも同じような習慣があり、月餅を食べます。韓国では松方(そんぴょん)という三色団子を作ってお供えします。
太平洋の島々の中にも、サトイモやタロイモなどをお供えし、秋の収穫祭をする国もあるそうです。
お子さまと一緒にお月見について知りましょう
お月見が近づいてきたら、お子さまと一緒にお月見に関する絵本などを読んでみてもいいですね。
また旧暦9月13日のお月見は十三夜といわれ、十五夜に続いてお月見をする日とされています。
今年のお月見には、美しいお月さまが見られますように。