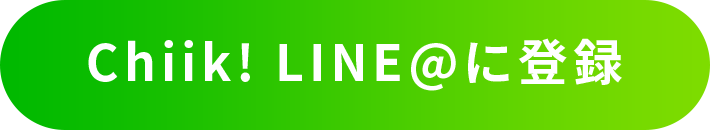当時は「なぜ私だけがこんなにツラい思いをしなければならないの」と思っていたのに、今となっては時計を巻き戻したいほど、懐かしく愛おしい記憶に。胃に穴が空きそうなほど悩んでいたことが、「悩みがあってよかった」とさえ思えるように。子育ての感じ方は、時間の経過とともに変化します。大きく育った子どもを前に、通りすぎた経験は、異なる記憶に置き換えられていくようです。
子育ては楽しく、もう戻ってこない尊い営みであることを、「経験してきたもの」は知っています。しかし、筆者を含めた経験者が、子育て真っ最中のころ、本当に子育てを「楽しい」と捉えていたかというと、その限りではありません。むしろ当初は辛く厳しく、必死にもがき苦しんでいたといっても過言ではありません。
決して「楽しい」だけではない、子どもとの日々。しかし、捉え方が変わると味わいも変わってきたりします。子どもを育てるという経験について、深めてみましょう。
子育てにおける「振り返り」の重要性と親子で取り組む3つのコツ
いつまでたってもなくならない悩み

赤ちゃんのころは、朝まで寝ることができない日々に悩み、成長とともに発達が気になり、学齢に達すれば勉強のことが心配になりだす。高学年にもなれば、悩みもなくなると思いきや、今度は思春期に戸惑い、受験のサポートと、子育ての悩みはいつまでも続きます。
なぜ、こんなにも悩むのかというと、それは大切な相手だから。大切すぎて、近視眼的になるから。もしも他人の子どもなら、客観的に成長を捉えることができ、そんなに苦しむこともないのでしょう。
もう一点、人間の子どもは自分では命を守ることができない状態で生まれてくることも、理由として挙げられるかもしれません。子育ては、「親である自分が頑張らなければ」という使命感から始まっているのです。「責任をもって」となれば、「これでいいのか」と不安にもなってしまいます。
大切な存在を持つというここと、成長を支えるということには、悩みがつきものと割り切った方がいいかもしれません。
捉え方が作り出す感情
嬉しい、楽しい、ツラい、苦しい。人間には様々な感情がありますが、実はこれらの感情は「捉え方」が作り出しているそう。
例えば点数が下がった時、「自分は無能だ」と捉えてしまえば、悲しい気持ちになりますし、「今回は残念だったが次回頑張ろう」と捉えることができれば、意欲が湧いてくるはずです。同じ事実なのに、その後の感情は「捉え方次第で」異なるということ。アルバート・エリスという臨床心理学者は「ABC理論」の中で、「事実が感情を作るのではなく、捉え方が感情を作る」と示しています。
子どもは、親の思うようには育ってくれません。うまくいかない経験をした際に、「なぜうまくいかないのか」「何が悪いのか」と犯人探しをするのはやめませんか。その先には、「私の子育てが間違っているのでは」といったネガティブな感情しか、沸き起こってこないから。こんなに頑張っている自分を、傷つける必要はありません。
捉え方を変える方法
では、どうしたら子育ての捉え方が変わるのか。うまくいかない経験をした時にも、犯人探しをせずにすむようになるのでしょうか。
「子ども目線になること」は、一つの助けとなりそうです。「子どもにはどんな景色が見えているのか」「この子は本当はどうしたいのか」と子ども目線になって、想像をしてみましょう。すると、いかなる子どもの行為にも、意味があることが見えてきて、悩みの捉え方が変わります。「なんでこの子は…」という捉えが「この子は〇〇をしたかったのかな…」となり、「なら、もう少し話を聞いてみるか!」と、ポジティブな感情が生まれそうです。
「仲間を作ること、つながりをつくること」も、大きな助けになるでしょう。他人の考え方や取り組みを知ることで視野が広がれば、今の悩みなど、大した悩みではないと思えるようになったりします。話を聞いてもらうだけでも、気持ちはかなりすっきりするはず。誰かと話をしながら、負担をどんどん手放していきましょう。無理に感情を変えることはできませんが、「まあ、いいか」と、捉え方が変化すれば、その後の感情もポジティブになります。
子どもを育てるという経験が教えてくれること

子どものいる生活には、「自分時間」はほとんどありません。「子どものため」で埋め尽くされた日々を過ごしながら、「私の人生これでいいのか」と感じてしまうこともあるのではないでしょうか。それでも、「子育て」には、大きな意味があると感じます。 「今だからこそ言える経験」であることを前提に、子育てという経験から得た価値についてまとめます。
柔軟な思考
親になった当初、勘違いしていたことがあります。それは子どものことを自分の分身のように思っていたこと。自分が好きなら子どもも好き。自分のあたり前は子どもにとっても当たり前。無意識に、こんな風に感じていたのです。
しかし、子どもは成長とともに、親との価値観の相違を見せつけてきてくれます。親にとっては戸惑うこともありますが、そんな経験を通して、自分と子どもは違う価値観をもった存在であることに気づいていきます。
子どもに何かを伝達しようと思えば、子ども目線になる必要があります。子どもの捉える世界を想像することによって、自分の考え方も柔軟に広がっていきます。気づけば自らの価値観も変化したり上書きされたり。「柔らかくなったね」と言われるようになりました。
社会とのつながり
子どもとは一人で育てて行く存在ではなく、社会全体で育てていく存在。子どもがいる暮らしには、社会とのつながりがあります。公園や図書館等、子育てをするまで気づかなかった地域の社会資源が、どんどん目に入ってくるようになり、接点ができてきます。
また、子どもという存在を通して、多様なネットワークも広がっていきます。学校に習い事、子どもの趣味やボランティア活動等。子どもを入り口としたつながりは、やがて大人同士のつながりに。ママ友とのランチ会は、ありがたいことに今もなお続いています。
自己有用感
人間の子どもは自分では命を守ることができない状態で生まれてきます。生理的早産とも言われ、生まれた直後から大人の関わりが必要になります。我が子の命を 「守る」ことからスタートする子育て。その思いは子どもが大きくなっても変わらず、「子どものため」の、時間が過ぎていきます。
誰かのために生きる姿勢は、「私がこの子の人生を守っている」と、自己有用感をもたらします。母親は子育てをすることで強くなると言われますが、それは子どもを守ることから得られる自信が背景にあるから。守られる存在であった「娘」は、母親になると「守る存在」になっていきます。
育成力
どんなに優秀な上司であっても、部下育成には苦労する等、人材育成には難しさがつきもの。相手の気持ちを汲み取って、相手が自ら成長したいと願う環境を整えていくためには、スキルを身につけるだけでは、なかなかうまくいかないのです。
子育てとは、一人の人間の成長を、長きにわたって支援し続けるということ。なかなかわからなかった子どもの本心を知る、エンパワメントを通して真なる自信を育てる、自分の感情をコントロールしながらも共感的に寄り添い、そして失敗経験を成功体験に変える等、子育ての日常には、様々な成長支援が埋め込まれています。
子どもを育てるとは、人を育てるということ。その経験は、人材育成にも役立ちます。
自分らしいキャリア
子どもとの暮らし、子ども中心の日々は、常に時間との戦い。子育てをしながらのキャリアには、一時的に制限がかかってしまうことも否めません。しかし、そのことで、仕事の効率化や、段取り力が増す等、自分自身の成長があることも事実です。家族と共に生活することで、共感力や表現力の高まりもあると感じます。頑張ったことに無駄なことは一つもなく、子育てをしたからこそ、生きる力が高まったとも言えるように思います。
また、子育てを通して新たな社会課題が見つかったり、情熱を感じる仕事に出会ったりすることも。筆者もそうであるように、子育て経験を通して、本当に自分が願うキャリアが見つかったという話もよく聞きます。

親は完璧な存在ではありません。子どもによって、少しずつ、少しずつ親になっていく、それが親のあり方なのでしょう。子育てが一段落するころ、ようやく子育てにはゆとりができ、そして捉え方が肯定的になっていきます。そして懐かしく振り返り、「子育ては楽しかった」となるわけです。子育ての感じ方は時間とともに変化していくもの。経験者として、それだけお伝えしたいと思います。
■ライタープロフィール

江藤真規
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了 博士(教育学)
株式会社サイタコーディネーション代表
クロワール幼児教室主宰
アカデミックコーチング学会理事
公益財団法人 民際センター評議員
一般社団法人 小学校受験協会理事
自身の子どもたちの中学受験を通じ、コミュニケーションの大切さを実感し、コーチングの認定資格を習得。現在、講演、執筆活動などを通して、教育の転換期における家庭での親子コミュニケーションの重要性、母親の視野拡大の必要性、学びの重要性を訴えている。著書は『勉強ができる子の育て方』『合格力コーチング』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『心の折れない子どもの育て方』(祥伝社)、『ママのイライラ言葉言い換え辞典』(扶桑社)など多数。
クロワール幼児教室
■江藤さんへのインタビュー記事はこちら↓
イヤイヤ期の言葉がけはタイプ別に!江藤コーチの子育てアドバイス①
子どもをやる気にさせるほめ術は?江藤コーチの子育てアドバイス②
学力向上ために6歳までにやるべき6つのこと。江藤コーチの子育てアドバイス③
■江藤さんの著書紹介
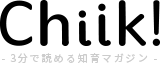

 江藤真規
江藤真規