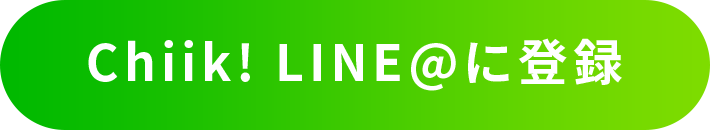「私はこう思うから!」自己肯定感が高く、自己主張ができるのは嬉しくも、親の意見に耳を貸さない我が子に、親はどう関わればいいのでしょう。子どもの気持ちを尊重することと、親が伝えたいことを我慢するのは、同義ではありません。子どもの気持ちを大切にしつつも、伝えたいことを伝える姿勢が、親には求められます。共感から始める伝え方の工夫、 「聴く」を基盤とした“コミュニケーションの習慣”を取り入れ、一人よがりではない、他者をも尊重できる子どもを育てていきましょう。
自分の考えをしっかりと持ち、堂々と主張する我が子。自己肯定感が育っている証拠であり、親にとっては喜ばしい成長のはずなのですが、その背景には「親の意見に耳を貸さない」「すぐに反発してくる」と戸惑う声も少なくありません。とはいえ、近年の教育現場や家庭は、「子どもの気持ちを尊重する」風潮に。「これでいいの?」と悩みつつも「親が言いたいことを我慢してしまう」ケースも増えている様子です。
自己主張をする子どもに、親がどのように意見を伝えることができるのか、家庭でできる工夫について考えていきましょう。
難しいと挑戦しない? 子どもの挑戦心を育むために親ができること
親の役割とは?
子どもの意見を尊重するのは大切なこと。答えを与えるのではなく、子どもが自ら考え、自己決定する機会を作ることはとても重要です。ただ、自分で考え自分で決めるためには、材料となる知識や経験も必要です。それらがなければ、気分次第の判断となってしまうからです。
近年は、「子どもの気持ちの尊重」というキーワードが広がるあまり、もしかもすると「親は意見しない」と間違った解釈が生み出されている可能性も。しかし、それでは子どもの経験の機会が乏しくなってしまいます。子育ての第一義的責任は保護者にあり、家庭の教育方針を決めるのは、親の責務であることを再確認し、必要なことはしっかり伝えられる関係性を築いていきましょう。子どもの言いなりになることと、子どもの気持ちを尊重することは別ものです。
「意見の主張」と「耳を貸さない」を分ける

その上で、やはり気になるのが「自己肯定感」というキーワード。日本人の子どもの自己肯定感が、諸外国の子どもと比較して低いとされる現在、「自分の意見や考えがあること」は是非とも肯定したく、親の意見の押し付けは避けたいものです。
そこでおすすめなのが、「意見の主張」と「耳を貸さない」を分けて考えること。今のお子さんは、「自分の意見を主張」しているのでしょうか。それとも「他人の意見に耳を貸さない」状況なのでしょうか。もしも後者なら、注力するのは「他者の意見を聞く姿勢」の育みです。「自分の意見があるのは素晴らしいことだね。では次に、お母さんの考えも聞いてくれるかな」と、「他人の意見を聞く」練習を重ねましょう。「聞いてくれてありがとう」と加えれば、他人の意見を聞くことに、得意意識を持ちそうです。意見の主張をやめさせる必要はありません。
“尊重”しつつ“伝える”ための3つの工夫
子どもが「自分はOK」と思う気持ちは、是非とも大切にしましょう。ここでは、子どもの気持ちを尊重しつつ、伝えたいことを伝えるための工夫を3点ご紹介します。
1.耳を貸さない理由を考える
なぜ、子どもが親の意見に「耳を貸さない」のか、その理由から考えてみましょう。
・耳を貸すことで誘導されてしまいそう
・自分の考えが否定されたと感じる
・親の意見は正論であるが、自分の置かれた環境にマッチしない
・親の価値観で評価されるのが嫌
・自分のことをわかってくれていない
例えば、このような理由が思い浮かびます。コミュニケーションは、どう伝わったかがゴールです。たとえ、「あなたの意見は間違っている」と否定語は使っていなくても、子どもが「否定された」と感じたのであれば、伝え方を見直していく必要があるということ。まずは、「なぜ、伝わらないのか」「なぜ耳を貸さないのか」、子どもの心の中を推測するところから始めてみましょう。
2.3つのステップを意識する

伝わらないなら、伝え方を変えましょう。伝えたいメッセージが伝わる3つのステップをご紹介します。
1.共感を示す
一番重要なのは、会話のスタート地点です。共感から始めましょう。最初の関わり方を間違えしまうと、子どもは耳に栓をしてしまいます。
・子どもと目線の高さを合わせる
・子どもの言葉を繰り返す
・「なるほど、そう考えるんだね」と子どもの気持ちを代弁する
こういったスキルを使うだけでも、共感的に寄り添うことができるようになります。
2. 自分の意見を「気持ち」として伝える
共感で、コミュニケーションの土台が整ったら、今度は親の意見を伝える場面です。ここで重要なのが、正解として伝えないこと。「親の意見は絶対」として伝えるのではなく、子どもが考え、選択する余白を残しておきましょう。
・「お母さんの意見を言ってもいいかな?」と前置きをしてから伝える
・「お父さんは〇〇と思うよ」と自分の考えを伝えるに留める
・「もしもお母さんだったら」と場面を設定した上で伝える
使う言葉によって、伝わり方は変わります。
3.対話をしながら決めさせる
親の意見を伝えた後は、子どもが選択をする段階に。対話をしながら決めさせると、子どもの納得感が高まります。
・AとBとどっちにしようか?
・先にやるとしたら、どっちにしたい?
・そう思う理由を教えてくれるかな?
もちろん「私はこう思うから!」と、当初の意見を押し通してくるかもしれませんが、親の意見を聞いた上での自分の意見なのか、自分しか存在しない世界での自分意見なのかで、その後の成長が変わってきます。
絶対に親の意見を通さなければならない場面では、理由とともに子どもに伝えます。「ここはお母さんの考えで進めるけど、あっちは〇〇ちゃんの意見通りにしようね」等、子どもの気持ちが尊重される場面も残しておくとよいでしょう。
3.「聴き合う」文化を家庭内に作る
耳を貸さないのは、家庭の中に「聴き合う文化」がないからかもしれません。コミュニケーションは、誰かから学ぶものではなく、見よう見まねでつかんでいくもの。子どものきき方・話し方は、意外と親のスタイルの模倣だったりするものです。
まずは親から、日常生活で「聴く」を意識してみませんか。傾聴です。親が子どもの話にじっくりと耳を傾ける機会を増やせば、子どもにもその「聴き方」が伝染し、知らず知らずのうちに「聴き上手」になっていく可能性も。
「話をききなさい」とする前に、親自身が「良い聴き手」となってしまいましょう。以下のスキルを駆使して、家庭の中に「聴きあう文化」を作ってみてください。
・アイコンタクト、相槌・うなづき
・「〇〇なのね」と、相手の言葉を繰り返す
・「こう言う理解でよかったかな」と、相手の言葉を要約する
他者の言葉に耳を傾けない人生と、積極的に聴こうとする人生では、得られる知識や経験が大きく異なります。「聴き方」は学校で学ぶことはありませんので、家庭の中に「聴き合う文化」を埋め込んでみてください。
自分の意見を主張できるのは、とても素晴らしいこと。時に頑固に見えるかもしれませんが、それは成長の証と捉え、「意見の主張」と「周囲の意見に耳を傾ける」の両方ができるよう、“尊重”と“伝える”のバランスを取っていってくださいね。
■ライタープロフィール

江藤真規
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了 博士(教育学)
株式会社サイタコーディネーション代表
クロワール幼児教室主宰
アカデミックコーチング学会理事
公益財団法人 民際センター評議員
一般社団法人 小学校受験協会理事
自身の子どもたちの中学受験を通じ、コミュニケーションの大切さを実感し、コーチングの認定資格を習得。現在、講演、執筆活動などを通して、教育の転換期における家庭での親子コミュニケーションの重要性、母親の視野拡大の必要性、学びの重要性を訴えている。著書は『勉強ができる子の育て方』『合格力コーチング』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『心の折れない子どもの育て方』(祥伝社)、『ママのイライラ言葉言い換え辞典』(扶桑社)など多数。
クロワール幼児教室
■江藤さんへのインタビュー記事はこちら↓
イヤイヤ期の言葉がけはタイプ別に!江藤コーチの子育てアドバイス①
子どもをやる気にさせるほめ術は?江藤コーチの子育てアドバイス②
学力向上ために6歳までにやるべき6つのこと。江藤コーチの子育てアドバイス③
■江藤さんの著書紹介
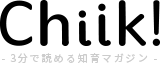

 江藤真規
江藤真規