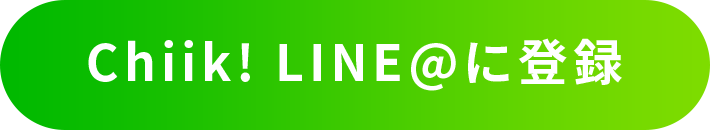集中力は上がったり下がったりするものです。その時の体調や気持ち、周囲の環境によって、浮き沈みします。意志力だけに頼ることもできず、「なぜ集中できないのか」と責めることで、自己肯定感が下がる等の二次的被害を生み出してしまうことも。集中力が低下していると感じる場合には、まずは原因を探ってみましょう。子どもが置かれた環境へのアプローチで、気づけば集中できている状況を目指します。
集中力低下の原因を考える
集中力の低下は、子どものみならず、現代社会においては大人も直面している課題です。やることが多すぎる、情報が多すぎる、ストレス過多や睡眠不足等、何らかの原因が背景に隠れています。自分のことなら、例えばオフの日を作ってリラックスする、日常生活を見直し睡眠時間を確保する等、集中力低下の背景要因への対処をしていくのかもしれません。
一方、子どもに対しては、集中力の低下を「やる気の低下」と紐付け、「集中しなさい」「もっと頑張りなさい」で片付けてしまいがち。しかし、これではうまくいきません。集中力低下の原因が解決されない限り、気持ちを切り替えようとしても、すぐに元に戻ってしまいます。
まずは、原因を考えてみましょう。集中力が低下していると感じたら、子どもが置かれた環境に注目です。部屋の空気や温度は快適でしょうか。雑音や気になるものが近くにあって、集中できないこともよくあります。SNSやメッセージアプリの通知が頻繁に来る環境は、集中力を大きく妨げます。周囲の人間関係も、集中力に影響を与えます。友達との関わりに関する悩みや、家族からの大きすぎる期待は、集中力を散漫にします。
集中していないことを責める弊害
大切な子どものことだから、すぐに良い結果が欲しくなってしまいます。「集中しなさい」と急かし、それでも集中していない姿を見れば、「なぜ集中できないのか」と責めてしまいます。時には「集中できないあなたは本当にダメだ」と、子どもを否定したり、「〇〇ちゃんは集中しているのに」と他者との比較をしたり、叱るという行為でなんとかしようとしてしまうことも。
しかし、これらの対応は返って逆効果になってしまいます。集中できないことを責められることで、子どもの世界から楽しさが消え、ストレスや不安を与えてしまうことで、自己肯定感が下がってしまうかもしれません。それによってさらに集中力は低下し、取り組み自体へのモチベーションも下げてしまいそうです。集中力低下を責められることによる、二次的被害です。状況をさらに悪化させないためにも、無理やり上げさせようとすることは、やめておいた方がいいでしょう。
集中力を高めるための5つのアプローチ

それでも、今の状況を看過できない場合には、どのような方法で子どもの集中力を上げることができるのでしょうか。子どもが幼少期だったころのことを思い出してみてください。気に入った遊びがあれば、きっと没頭していたことでしょう。「やってみたい!」と思ったら、集中して何度も練習をしていませんでしたか?キーワードは、自然と集中できる環境作りです。5つのアプローチ法をご紹介します。
1.いいところを見つけて褒める
集中力が先か、行動が先か。いずれの考え方もあるのでしょうが、親にできる取り組みは、子どもの行動を促すこと。0から1に動くためのサポートをしましょう。
「自分には無理だ」「自分にはできない」等、ネガティブな気持ちになると、人は行動できなくなってしまいます。例えばいいところを見つけて褒める等を心がけて、子どもが自信を持って行動できる環境を作りましょう。
「自分はできる」と思えれば、行動が始まります。行動してみたら面白くなり、気づけば集中していたということもあるでしょう。「頑張ったね」と伝えることで、もっとやってみようと集中していることもあるはずです。
2.適度な運動・休息を取らせる
集中するためには前提があります。身体の状態が整っていなければ、集中することができません。「もっとできる」「もっと頑張って」と詰め込むばかりでなく、たまには「引き算」することも意識してみてはどうでしょう。
やらなければならないことをあえて後回しにして、思い切って休んでみる。勉強も気になるけど、適度に体を動かすことを優先させる。これだけでも、気持ちがリセットされて、集中力が増すかもしれません。
体と心は両輪です。ご自身の経験に当てはめてみれば、体がいっぱいいっぱいでは集中できないことは明らかでしょう。
3.習慣化させる
朝起きたら顔を洗う。歯磨きをする。人に会ったら挨拶をする。これらは習慣となっているため、行動するにあたっての負荷がかかりません。
もしも好きなことなら、たとえ習慣になっていなくても、すんなりと行動できるのですが、苦手なことだったら、行動することが億劫になってしまいます。集中できない背景に苦手意識がある場合は、習慣化することがおすすめです。例えば苦手な算数になると、集中力がなくなってしまう場合には、算数の学習の習慣化を試みましょう。
習慣化するためには、ハードルを極力下げて、同じことを毎日継続すること。決して欲張らずに、5分でもいい、毎日算数を解いてみることから始めてみませんか。小さな成功体験を重ねながら継続することが大切です。そのうち「やっていないと気持ち悪い」という習慣ができているかもしれません。
4.適切な環境を整える
意外と見落としがちなのが、物理的な環境を整えること。例えば家庭学習なら、適切な学習環境を考えます。
隣に誰かがついている環境がいいのか、一人静かな環境がいいのかは、子どもを観察して決めると良いでしょう。他に気になるものがあると、集中しづらくなってしまいます。「ここにマンガがあっても集中できる」と子どもは言うでしょうが、見えるところにあれば、気になってしまうのは当然です。優しく諭して親が管理できるといいですね。
また、空気や温度、音などの状況によっても、集中力は変わります。二酸化炭素の充満は、集中力低下につながります。適度に空気を入れ替え等で、適切な環境を作ってください。
5.なりたい自分をイメージする

最後にお伝えしたいのは、集中するための目的です。憧れの気持ちは、行動の大きな後押しになります。「あんな風になりたい」「こんなことに挑戦してみたい」。このような気持ちが芽生えてくれば、俄然集中力も出てくることでしょう。
「つまらないけど頑張ろう」というアプローチは、幼少期の子どもには通用しません。「頑張ろう」の代わりに、「これができたら〇〇みたいに素敵だよね」と伝えてみませんか。「〇〇に近づいたね」と、成長している姿を伝えるのも効果あり。いやいやでも集中できるのは、使命感や責任感を感じるようになってからかもしれません。子どもの世界は、楽しさありきの世界です。
■ライタープロフィール

江藤真規
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了 博士(教育学)
株式会社サイタコーディネーション代表
クロワール幼児教室主宰
アカデミックコーチング学会理事
公益財団法人 民際センター評議員
一般社団法人 小学校受験協会理事
自身の子どもたちの中学受験を通じ、コミュニケーションの大切さを実感し、コーチングの認定資格を習得。現在、講演、執筆活動などを通して、教育の転換期における家庭での親子コミュニケーションの重要性、母親の視野拡大の必要性、学びの重要性を訴えている。著書は『勉強ができる子の育て方』『合格力コーチング』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『心の折れない子どもの育て方』(祥伝社)、『ママのイライラ言葉言い換え辞典』(扶桑社)など多数。
クロワール幼児教室
■江藤さんへのインタビュー記事はこちら↓
イヤイヤ期の言葉がけはタイプ別に!江藤コーチの子育てアドバイス①
子どもをやる気にさせるほめ術は?江藤コーチの子育てアドバイス②
学力向上ために6歳までにやるべき6つのこと。江藤コーチの子育てアドバイス③
■江藤さんの著書紹介
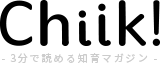

 江藤真規
江藤真規