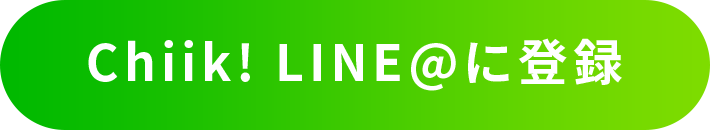新しい習い事は、新たな出会い。始める時には、ワクワク感が高まります。特に最近は、「やり抜く力」や「仲間とともに頑張る力」等、勉強からは得られない経験にも注目が集まり、習い事への期待が高まってきているようです。
しかし、一旦始めた習い事をずっと継続するには、難しさもあります。子どもの方から、「もう、やだ…」と言い出すこともありますし、一切練習をせずに、「ただ、通っているだけ」の状況に、親の方が疑問を感じることだってあるでしょう。だからと言って、さっさとやめるわけにいかないのが、子どもの習い事。せっかく始めたことを手放すには躊躇があります。始めるは易し、やめるは難し。習い事のやめ時について、考えてみましょう。
(ここで捉える習い事とは、プロの道を進んでいるケースを外します)
習い事の「やめ時」のサイン
自分の状況や子どもの現状を客観的に見るのは難しいもの。「まだ、できる」「続けるべきだ」「続けていれば、いつかは成果が出てくる」。親の願いが、子どもの現実を見る目を曇らせます。
しかし、親の思い込みやエゴで、無理やり子どもを習い事に縛り付けていたとしたら、置き去りにされた心は、成長できなくなってしまいます。子どもが示す、習い事の「やめ時のサイン」を確認しておきましょう。
過度なストレス反応が出ているとき
全てのストレスがよくないわけではありません。ストレスがあるから、頑張ることだってできるものです。しかし、習い事によるストレスが、食欲不振や不眠等の身体反応を引き起こしている場合には、やめることも視座にいれた方がいいかもしれません。髪の毛をむしる等の自傷行為にまで発展しているなら、心を休ませるためにも、一旦手放す勇気が必要です。
生活面に悪影響が出ているとき
習い事には、送迎や家での練習も含め、親の労力を要します。「子どものため」には何でもやってあげたいにせよ、その頑張りが持続可能かどうかは、判断する必要があるでしょう。
過剰な習い事によって、家族がギスギスしてしまう。家族時間が圧迫され、日常生活が上手く回らなくなる。習い事の費用が経済状況に合っていない場合も、やめる判断が必要かもしれません。もちろん、子ども自身の基本的な日常生活が崩れてしまう場合にも、持続可能か否か、要検討です。
子どもが本気で「やめたい」と言っているとき
面倒だから、今日は友達とあそびたいからなど、子どもが「習い事をやめたい」ということは、よくあります。一時的な感情からくるものですので、あまり気にする必要はありません。しかし、本気で「やめたい」と言ってきた場合には、子どもの声に耳を傾けてください。本気かどうかは、親のカンで判断です。
なぜ、そう思うのか。いつからそう感じていたのか。「やめたい」の背景には、深刻な問題が潜んでいる可能性もあったりします。子どもが被害者になる前に、気づいてあげましょう。
やめるか継続するかを判断する際のポイント

やめるべき理由はないが、このまま続けることにも躊躇がある。続けたい気持ちもあるが、そろそろやめ時と思うこともある。最終的には親が決めるにせよ、子どもの気持ちも大切にしながら判断したいものです。判断するためのポイントをご紹介します。
子どもの様子を観察する
あくまで習い事をするのは子どもです。子どもの気持を尊重するためにも、子どもの様子を観察しましょう。親の気持ちを痛いほどに感じている子どもは、本当の気持ちを言葉にしません。子どもの様子を観察して、こちら側から察する必要があります。やめるも継続するも、起点となるのは子どもの気持ちです。
子どもと話をしてみる
子どもが自分の気持ちを話さない背景には、「親への気遣い」以外に、話す機会がないこともあります。コミュニケーションの不足です。「子どもにはまだわからないから」という思い込みを外して、子どもの意見を聞いてみてはどうでしょう。親の気持ちと子どもの気持ちがズレていることもありますし、「〇〇ちゃんはどうしたい?」と聞かれることで、子どもの自己肯定感が高まります。自己決定の習慣をつけるためにも、自分の意見を話すことはよい経験となるはずです。
続けたい/やめたい理由・メリット/ディメリットを書き出してみる
やめるか継続するか。頭の中でぐるぐると回る2つの考えは、なかなか出口に到達しません。「考える」を「書き出す」に置き換えてみましょう。書き出すことで、「考え」は可視化され、整理されていきます。紙を2つに折り、半分には続けたい理由を。もう半分にはやめたい理由を。書き出すのは、子どもの気持ちではなく、自分自身の気持ちです。
「やめ時」を探るためには、やめることのメリット・ディメリットを書き出してみてもいいでしょう。やめることで得られることがあると気づけば、やめる際の罪悪感は減るかもしれません。
これまでの習得状況を俯瞰する
習い事をやめると、せっかくの今までの努力が無駄になってしまう。このような気持ちが、やめることを難しくします。しかし実際には、経験したことは全て、子どもの中に残っているものです。これまでに身に着けてきたことを振り返ってみましょう。できるようになったこともたくさんあるでしょうし、内面的にも、きっと大きな成長があったはず。ここまでの取り組みの成果を理解できれば、一旦この習い事はここまでにしようと、区切りがつけやすくなります。やめるとは、決して諦めるということではありません。区切りをつけるということです。
受験など、他の目的がある時の考え方
例えば受験等、他の目標ができた時には、「限られた時間でどうやりくりするか」という新たな問題が浮上します。習い事は楽しんでいるが、受験勉強も本格的になってきた。体力づくりのためにも習い事は継続させたいが、塾の宿題もやりきれていない。習い事をやめることでメンタルが崩れてしまうことも心配。様々な要因が絡み合っているため、非常に判断が難しくあります。
最終的には、親子で話をして、子どもが納得する解に向かうことが大切ですが、その前に、親としての考えを明確にしておきましょう。親の気持ちにブレがあっては、話し合いになりません。
より本格化していく受験勉強に、一体どれだけの時間がかかるのか、試験当日までの日数を具体的に書き出し、シュミレーションをしてみます。一日何時間の勉強時間が確保できるのか、実際にはどれだけ必要そうか。先輩の体験談も参考にしてみるといいでしょう。なんとなく難しそう。なんとなく不安。このような状況では、適切な判断ができません。
その上で、やめる方向に向うのなら、やめることによる弊害を最小限に抑えるための工夫をします。例えば、やめるのではなく「休む」ことにする。受験が終わったら再開することを視座にいれます。受験の◯ヶ月前になったら習い事をやめる等、やめる期日を決めておくのも一つの方法です。それまで両輪で頑張ることで、子どもの精神は鍛えられるでしょう。勉強の成果は、かならずしも費やした時間に比例しているわけではありません。子どもが気持ちよく、受験勉強にスイッチを入れられるよう、まずはご自分の不安を払拭してください。
大切なやめた後のフォロー

忙しすぎるからと習い事をやめたのに、習い事をやっていた時の方が生活が安定していた。早く寝ることもできていたし、勉強もよくやっていた。こんな話を耳にすることも少なくありません。やめた後の時間の使い方は、やめる前に決めておくといいでしょう。やめた後に浮いた時間を、ただダラダラと過ごしてしまっては、子どもにとってもいいことはありません。
「やめた後にできる時間で何をしようか」こんな話し合いができていれば、やめることで、再び新たな出会いをつくることができそうです。
■ライタープロフィール

江藤真規
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了 博士(教育学)
株式会社サイタコーディネーション代表
クロワール幼児教室主宰
アカデミックコーチング学会理事
公益財団法人 民際センター評議員
一般社団法人 小学校受験協会理事
自身の子どもたちの中学受験を通じ、コミュニケーションの大切さを実感し、コーチングの認定資格を習得。現在、講演、執筆活動などを通して、教育の転換期における家庭での親子コミュニケーションの重要性、母親の視野拡大の必要性、学びの重要性を訴えている。著書は『勉強ができる子の育て方』『合格力コーチング』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『心の折れない子どもの育て方』(祥伝社)、『ママのイライラ言葉言い換え辞典』(扶桑社)など多数。
クロワール幼児教室
■江藤さんへのインタビュー記事はこちら↓
イヤイヤ期の言葉がけはタイプ別に!江藤コーチの子育てアドバイス①
子どもをやる気にさせるほめ術は?江藤コーチの子育てアドバイス②
学力向上ために6歳までにやるべき6つのこと。江藤コーチの子育てアドバイス③
■江藤さんの著書紹介
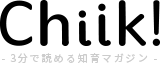

 江藤真規
江藤真規