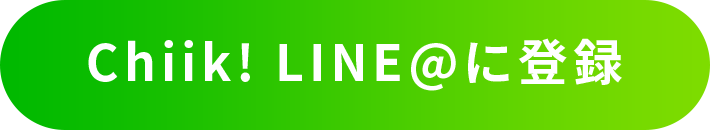親の目はどうしても「課題」に向かいがち。願う子ども像と目の前の“この子”を比較して、あれができていない、これもまだだ…となってしまいます。子どもが楽しくあそんでいると、「そんなことをしていないで、早くやるべきことをやりなさい」と言ってしまいます。
しかし、子どもにとってあそびは、何より大切な営みです。あそびの意味を再考し、あそびのレパートリーを広げましょう。日常生活に取り入れられる工夫をご紹介します。
幼児期は学びの芽生え期と言われています。「なぜだろう?」と深めてみたり、「もっと知りたい」と広げてみたり、「やってみよう!」と挑戦してみたり…。これらは幼児にとっての学びです。
「あそび」は「学び」の原点
決まったゴールがあるわけではありません。決まった教材があるわけでもありません。自分の興味関心に合わせて、自分のペースで進んでいく。まさに「好きなようにあそぶ」経験が、幼児にとっての学びなのです。
小学生になると、学びの様相は変わります。学年ごとに、ある程度の決まったゴールが設定され、そこに向かって皆で一緒に進んでいくことが求められるように。そのための基盤となるのが、幼児期のあそびです。あそびは学びの原点です。十分にあそび、学びの芽生えを楽しんでいきましょう。
教えられて覚えるものじゃない!?暮らしの中から、子どもが身につける「学び」とは
非認知能力って何?

近年、耳にする「非認知能力」という言葉。数値化できる学力等とは異なる、心や社会性に関する力のことを言います。「あと伸びする力」とも呼ばれ、非認知能力を身に着けた成果は、後になってから表れてくるそう。また、この力は幼児期にこそ大きく育つことも、明らかとされてきています。
では、幼児期に何をすればいいのでしょう。あそびです。しかし、「非認知能力を育てるために」と限定的に考えてしまうと、豊かなあそびとはかけ離れた方向に向かってしまいます。子どもが主体的にあそぶ。あそびたいようにあそぶことを、意識したいものです。
🔻非認知能力と遊びに関してはこちらの記事もおすすめです。
子どものあそびのレパートリーを増やそう! 5つの工夫
とはいえ、親子共々忙しい日常。不本意ではありつつ、どうしてもテレビやYouTubeに頼ってしまいそう…。それを回避するためにも、あそびのレパートリーを増やしませんか。家庭でできるちょっとした工夫を5つ紹介します。
1、子どもの世界を大切にしよう
子どもはあそびを見つける天才です。乳児期の探索活動から始まり、興味のあるものに関心を寄せ、自らおもしろさを見つけます。ものと対話をしながら。自分と対話をしながら…。
子どもを観察し、「今、没頭してあそんでいるな」という時には、声をかけたりせずに、見守りましょう。「それは何?」「何をしているのかな?」等、良かれと思って投げかけた言葉が、子どもを楽しいあそびの世界から引き離してしまうことにも。あえて黙る。あえて静かに見守ることで、子どもは自分の興味に合わせて存分にあそぶことができます。
2、自由に作ってみよう
子どもはみんな、アーティスト。新しいものを生み出す才能に満ちあふれています。大人の視点で「上手、下手」と評価することなく、子どもが作り出す世界を覗いてみませんか。
例えば部屋の片隅に、工作コーナーを作る。そこに廃材をストックしておけば、好きな時に、好きなようにあそぶことができます。レジャーマットを敷いておけば、汚れも気になりません。箱、紙、紐、袋…。紙、木、プラスチック、布…。見た目、感触、大きさ等、多様な素材を集めておくと、想像力が一層掻き立てられます。保育園帰りに見つけた木の実や葉っぱだって、格好な素材となるはずです。
お絵かきをする際にも、子どもの自由な表現を大切に。「これはなんだろう」と思うような絵にも、子どもなりのストーリーがあるのです。絵を描くのは、画用紙だけではありません。包み紙を広げれば、大きな絵が描けますし、ガラス窓に書いても楽しいですよ。お風呂の鏡や窓ガラスの結露も、楽しいキャンパスとなるはずです。
3、外に出てみよう

近所に公園があるなら、一度訪れてみませんか。暑かったり寒かったり、昨今は外あそびに適する日が減少傾向にありますが、それでも工夫次第であそべる時間帯はあるように思います。
外の世界は、子どもが自由を満喫できる世界です。思いっきり体を動かすこともできますし、季節の変化を感じ取ることもできます。植物を手にとってみたり、生き物と触れ合ってみたり。家ではできない様々な発見があるのが戸外です。子どもは何かを集めることが大好きですので、外に行く時には、かごや袋を持っていくと役立ちます。
同じ葉っぱにも、いろいろな形があることから、観察眼も育つでしょう。手にしたダンゴムシに命があることを知り、優しい気持ちが自然と芽生えてくるかもしれません。五感を使ってあそべるのが、外あそびの大きな価値です。
また、家族以外の人との出会いがあるのも、外あそびの魅力です。少し上の子どもへの憧れの気持ちは、何よりも大きな動機づけになりますし、何気なく交わす他者とのやり取りから、子どもは社会性を身に着けていきます。
4、からだを動かそう
体を動かす経験を、沢山させましょう。もちろん戸外で体を動かすのは一番の経験。走ったりジャンプしたり。バランスを取ったり転がったり…。思いっきり体を動かすことから、多様な運動機能の発達が期待できます。しかし、たとえ外に出られなかったとしても、体を動かすことを諦めないでください。マンション等では、様々な配慮が必要ですが、できる限りの工夫をして、動く経験を取り入れましょう。
例えば、お手伝いはどうですか。椅子に登ったり降りたり、背伸びをしたり、つま先で歩いてみたり。大きくなってみたり、小さく丸まってみたり。家事には様々な体の動きが含まれているのです。お掃除や窓拭き、買ってきたものをしまったり運んだり、ゴミ捨てやおふろ掃除、他にもいろいろありますね。お手伝いは、体を動かす楽しいあそびに置き換わります。是非工夫をしてみてください。
5、ごっこあそびを楽しもう
何かの真似事ができるようになってくると、ごっこあそびの始まりです。一人で何かになりきってあそんだり、役割分担を決めてあそんだり。そのうちに、イメージを共有しながらあそぶようになったり、物語を設定してあそぶようになったり、ごっこあそびは成長とともに変化していきます。
ごっこあそびを通して、想像力、表現力等、様々な力も育まれます。子どもが何かになりきってあそびだしたら、子どもの想像の世界を一緒に楽しんでみましょう。
ごっこあそびは、いつでもどこでも始まります。ままごとセットの玩具がなくても、空き箱を見立てて、おままごとができますし、お手伝いの延長線上に、ごっこあそびが始まることもよくあります。ダンボールや養生テープ、使わなくなったシーツ等は、ごっこあそびの世界を広げるために役立ちます。
子どものあそびに正解はない
あそび方に正解はありません。今の住環境に合わせて、子どもが自由にあそべるよう、是非工夫をしてみてくださいね。できるだけ制限をかけずに。できるだけ大人がコントロールせずに。環境作りに工夫をすれば、きっと豊かなあそびがはじまることでしょう。子どもはあそびの天才です。
■ライタープロフィール

江藤真規
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了 博士(教育学)
株式会社サイタコーディネーション代表
クロワール幼児教室主宰
アカデミックコーチング学会理事
公益財団法人 民際センター評議員
一般社団法人 小学校受験協会理事
自身の子どもたちの中学受験を通じ、コミュニケーションの大切さを実感し、コーチングの認定資格を習得。現在、講演、執筆活動などを通して、教育の転換期における家庭での親子コミュニケーションの重要性、母親の視野拡大の必要性、学びの重要性を訴えている。著書は『勉強ができる子の育て方』『合格力コーチング』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『心の折れない子どもの育て方』(祥伝社)、『ママのイライラ言葉言い換え辞典』(扶桑社)など多数。
クロワール幼児教室
■江藤さんへのインタビュー記事はこちら↓
イヤイヤ期の言葉がけはタイプ別に!江藤コーチの子育てアドバイス①
子どもをやる気にさせるほめ術は?江藤コーチの子育てアドバイス②
学力向上ために6歳までにやるべき6つのこと。江藤コーチの子育てアドバイス③
■江藤さんの著書紹介
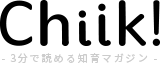

 江藤真規
江藤真規