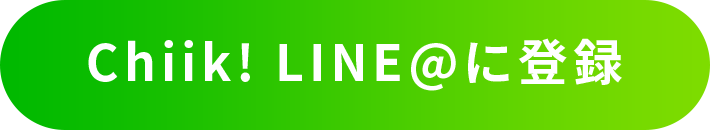何度言ってもやる気にならなかった子どもが、突然机に向かいはじめた!「行きたくない」と言っていたピアノなのに、急に練習をし始めた。
子育てをしていると、こんな場面に遭遇することもあるのでは…。子どもはある時急に変化したり、突然成長したりするものです。昨日と今日では、まるで別人。親としては、その変化に大きな喜びを感じますが、「一体何が起きたのだろう?」と、一方では不思議さも感じます。
心が動く背景には、本当にやりたいこととの出会いや、自分ならできるという自信、自分がやらなければならないという責任感があったりします。「誰かのため」という気持ちが、むしろやる気につながることだってあるでしょう。突然オンされるやる気の背景を洗い出し、そこから逆算してみれば、「自律的なやる気を育む環境づくり」のヒントが見えてくるかもしれません。
やる気がない!と決めつけないで
子どものやる気は、「〇〇をしたから」と、一つの理由があって出て来るものではありません。ずっと低迷していたやる気が、明確な理由なくして、突然大きくなることだってあるものです。
しかし、親の目はいつも「現実」に向かいがち。今やっていなければ、「やる気がない」ように見え、今動いていないなら、「挑戦心がない」と見えてしまいます。そして、決めつけが始まってしまいます。「この子はやる気がない」「この子は挑戦しない」と。子どもはある日突然変わることを信じて、ネガティブな決めつけは、できる限り排除していきましょう。
余計な一言でやる気を減退させない
「今ころやる気を出したって…」
「もっと早くやる気になればよかったのに」
「どうせ、長続きしないんじゃない?」
「お母さん言ったでしょ。やろうと思えばできるのよ」
「お母さんの言った通りに頑張ったからよね」
これらは、せっかく出てきたやる気を減退させてしまう言葉かけ例です。突然出てきた子どものやる気を素直に受け入れられずに、照れ隠しで余計な一言を言ってしまったり、親の手柄にしてしまったり。
しかし、これではせっかく出てきたやる気が減退してしまいそう。急にやる気になった時こそ、親は大騒ぎせずに、温かく見守っていく姿勢が必要です。
子どものスイッチが入る時ってどんな時?

子どもが急に行動を変える背景には、どのような要因があるのでしょうか。ここでは、「子どものスイッチが入る時」の背景要因を探ってみます。
何がしたいのかが見えた時(自己理解の深まり)
自分は何がしたいのかが見えた。本当の自分は何と言っているのかがわかった。こういった「自己理解」が深まることで、子どもは自律的に行動するようになります。自分自身が、真にやりたいことが見つかることで、「やらされていた」ことが、「自分のため」に置き換わり、自分ごと化が進むからです。
「そうだ、自分はこれがやりたかったんだ」が見えるきっかけは、様々です。例えば、憧れを感じるような人との出会いや、たまたま観た映画の一場面。雑談等のふとしたきっかけから気づきが起きることだってあるでしょう。言ってきかせるより、自ら気づくことの方が、圧倒的に行動変容を起こします。
自分ならできる!と思えた時(成功体験の積み重ね)
やる気の背景には、「自分ならできる!」という思いがあります。とくに、「あの時私はできた」といった過去の成功体験は自信の根拠となり、「次もできるかもしれない」という思いにつながります。
小さな成功体験を積み重ねることで、「私は努力することができる」「私は頑張ることができる」といった気持ち(自己効力感)が育てば、「私ならきっと大丈夫」と、挑戦心を持つことができるようになるでしょう。焦らずゆっくりと小さな成功体験を積み重ね、子ども自身が「自分ならできる」と思える時がくるのを待ちたいものです。
そのタイミングは子どもによって異なります。早ければいいということでもありません。時間をかけて、たくさんの経験を積んだからこそ、ようやく表出された自信が、揺るぎないものとなっているのかもしれません。
自分がやらねば!と思った時(責任感)
たとえば、一冊の本との出会いで他人の気持ちがわかるようになった。自由研究を通して社会課題に気づき、社会の一員として何ができるのかを考えるようになった。自分はないがやりたいのか(want)、何ができるのか(can)という軸だけでなく、自分は何をすべきなのか(must)という意識が芽生えることで、急に行動がはじまることもあります。
責任感とも言える力は、自分の役割を果たすための意欲をわかせ、行動を加速させます。誰かから褒めてもらえるから、ご褒美をもらえるから等の外的な要因に頼ることなく、自らの行動をかきたてる力です。
誰かのために頑張りたいと思えた時(社会性の向上)
本気になるのは、自分のためだけではありません。「誰かのために」「社会のために」、このような気持ちも、やる気に大きく影響を与えます。自分のためより、むしろ大きな力を発揮することもあるでしょう。
「〇〇のために」といった気持ちは、対象との出会いによって、突然芽生えます。知識が広がり、経験も増えることで、子どもの視野が広がり課題意識も高まります。自律的にやる気になり、急に行動が始まっている背景には、大切な誰かの姿や未来の景色が見えているのかもしれません。
自律的なやる気を引き出すために親ができること

やる気のスイッチは、自分にしか押せません。何らかの理由があったり、複数の要因が絡み合ったりして、子どもがスイッチをオンすれば、突然子どもの行動が変化するということ。なので、そのタイミングは、親には予想がつかないのです。
では、自律的なやる気を引き出すために、親にはどのようなサポートができるのでしょう。子どもが自分で考えて行動できるよう、ある程度の自由は必要です。全てを親がコントロールしてしまっては、子どもの心が動きません。
失敗を恐れないような環境を作り、多様な経験をさせることも大切です。経験をしてこそ、やりたいことが見つかりますし、経験を通して視野が広がることで、責任感が育まれます。そもそも、トライアンドエラーでやってみなければ、成功体験は積めません。
受容と共感を大切にした子どもとの対話も、ぜひ意識しましょう。満たされた自分の気持ちは、誰かのために頑張りたいという心持ちを呼び起こすかもしれません。
子どもが急なやる気を見せた時には、その変化を温かく見守りましょう。過度な介入は、せっかく芽生えた自律的なやる気を摘み取ってしまいます。子どもは成長する主体です。自分の力で成長していきます。
■ライタープロフィール

江藤真規
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了 博士(教育学)
株式会社サイタコーディネーション代表
クロワール幼児教室主宰
アカデミックコーチング学会理事
公益財団法人 民際センター評議員
一般社団法人 小学校受験協会理事
自身の子どもたちの中学受験を通じ、コミュニケーションの大切さを実感し、コーチングの認定資格を習得。現在、講演、執筆活動などを通して、教育の転換期における家庭での親子コミュニケーションの重要性、母親の視野拡大の必要性、学びの重要性を訴えている。著書は『勉強ができる子の育て方』『合格力コーチング』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『心の折れない子どもの育て方』(祥伝社)、『ママのイライラ言葉言い換え辞典』(扶桑社)など多数。
クロワール幼児教室
■江藤さんへのインタビュー記事はこちら↓
イヤイヤ期の言葉がけはタイプ別に!江藤コーチの子育てアドバイス①
子どもをやる気にさせるほめ術は?江藤コーチの子育てアドバイス②
学力向上ために6歳までにやるべき6つのこと。江藤コーチの子育てアドバイス③
■江藤さんの著書紹介
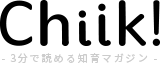

 江藤真規
江藤真規