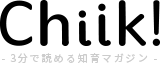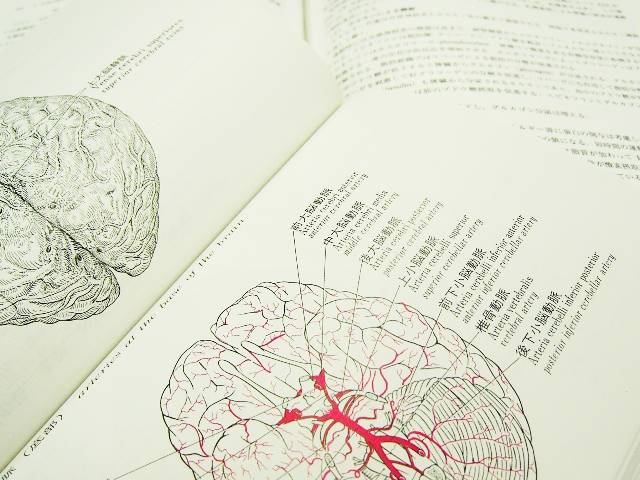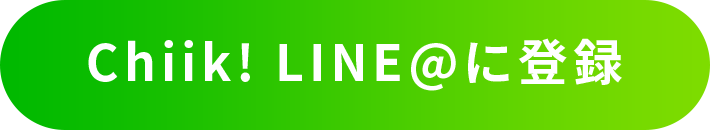2016年09月11日 公開
手と脳をきたえてトップスイマーに!?池江璃花子選手の秘密とは
リオ・オリンピックでは惜しくもメダル獲得ならずでしたが、大勢いる日本選手団のなかでも、光り輝く才能で注目を浴びていたのが競泳の池江璃花子選手です。小さい頃から水泳の特訓を積み重ねてきたのはもちろんですが、それ以外にも池江家独特の教育が彼女の才能開花に貢献したようですよ!
リオ・オリンピックでは惜しくもメダル獲得ならずでしたが、大勢いる日本選手団のなかでも、光り輝く才能で注目を浴びていたのが競泳の池江璃花子選手です。小さい頃から水泳の特訓を積み重ねてきたのはもちろんですが、それ以外にも池江家独特の教育が彼女の才能開花に貢献したようですよ!
「天才型ではなく努力型」の選手
水泳女子日本代表として、16歳で日本国民の期待を背負う存在となった池江選手。しかし彼女が抜きん出た成績を残すようになったのは中学入学以降で、それ以前はライバルにおくれをとっていたそうです。
彼女のコーチは「技術や泳ぎのセンスがあるのはもちろんだが、練習を一生懸命やってきた日々の積み重ねが結果につながっている」と池江選手を評価しています。つまり池江選手は天才型ではなく努力型の選手だということです。
「握る」ことで脳の基礎をつくった!?
では、池江選手はどんな努力を重ねてきたのでしょうか。池江選手というと必ず出てくるエピソードが、「生まれて半年くらいになるとお母さんの手を握ってぶら下がっていた」という驚異的な身体能力!お母さんは彼女のおむつを替えるときに、自分の指を握らせて握力を高める訓練をしていました。なんと生後2カ月になると「うんてい」の練習をはじめたというから驚きです。
「握る」という動きは、単に上半身を強化するだけでなく、手の神経を刺激して脳細胞の成長を促す効果もあるといわれています。「うんてい」こそが、池江選手の才能の基礎となったのかもしれませんね。
脳を鍛えた→水泳も上手くなった!?
3歳で水泳をはじめるより先に「七田式」の教育を受けていた池江選手。七田式といえば「右脳教育」をうたっていることで有名です。視覚・聴覚・触角を十分に刺激して、子どもの右脳の発達を促すのが七田式です。これが池江選手の才能開花にどの程度影響したかはわかりませんが、お母さんのお話によれば、物事を理解したり記憶したりするスピードはとても早くなったそうです。
池江選手は一般の子どもよりも泳ぎの技術を早くマスターできたので、どんどん上級のコースに進んでいきました。すると一緒に練習する仲間のレベルもアップしていくので、それが新たな刺激となり、さらに練習に励む……という良い循環がおきます。それが現在の池江選手の地位を築いた背景にあるといえそうですね。
世界でたたかえる身体とセンスは「うんてい」が育てた!?
池江選手は中学3年間で身長が15cmも伸び、170cmになりました。特筆すべきはリーチの長さで、なんと184cm!外国人選手にも引けをとりません。優れた水泳の技術を活かせる大きな身体に成長したことで、タイムもうなぎのぼりに!
彼女のリーチが長い原因は幼少期から欠かすことのなかった「うんてい」にあるかもしれません。
うんていは手や腕や肩の細胞を刺激し、骨や筋肉の成長を促すよう脳に働きかけるからです。うんていによって「物をつかむ」感覚が鋭くなり、水をとらえるセンス=水泳の技術向上につながったと考えることもできます。
ライバルの存在が「良い刺激」になるには?
池江選手のコーチによると、小学生までは彼女より優秀な同年代の選手がたくさんいたそうです。池江選手は幼い頃から負けず嫌いでまねをしたがる性格でした。水泳もお兄さんたちが習っているのを見てはじめたといいます。仲良しだった全国のライバルたちが優れた成績をどんどん残す様子を見て、池江選手は「負けないぞ!」と奮起しました。
小さい頃からうんていや七田式で体と脳を鍛えてきたことで、努力することをまったく苦にしない性格がここで大活躍!「自分はダメだ……」と落ち込むのではなく、「もっと努力して追いつこう!」とプラスに考えることができたのです。
「努力は無駄にならない」を子どもに教えよう!
池江選手の場合、「努力すれば結果を出せる」という経験の蓄積が、壁にぶちあたったときにめげるのではなく、さらなる努力を己に課すというプラス思考につながっています。
彼女の親御さんが実践したさまざまな子育て法が万人に当てはまるわけではありませんが、「努力が無駄にならない」という体験をいかに多く子どもに与えられるかという点で、大いに参考になるのではないでしょうか。