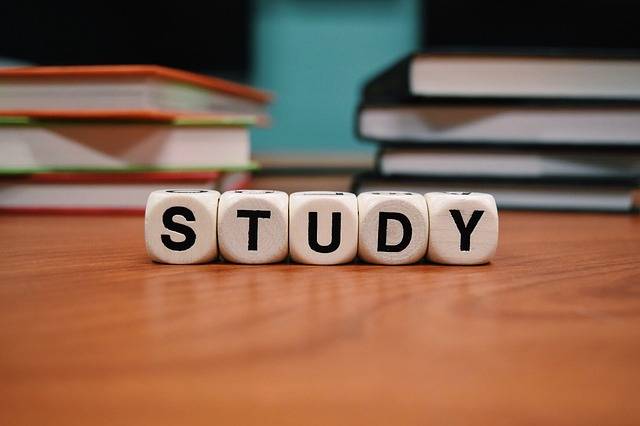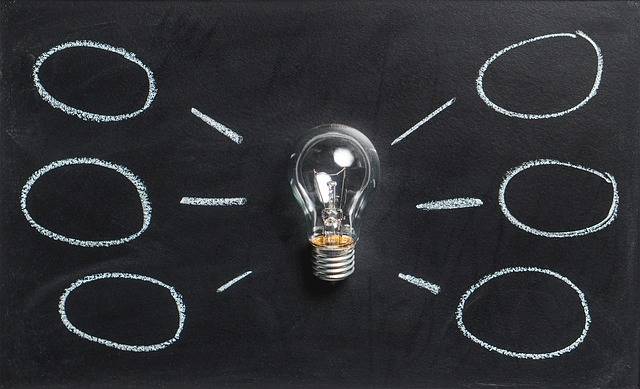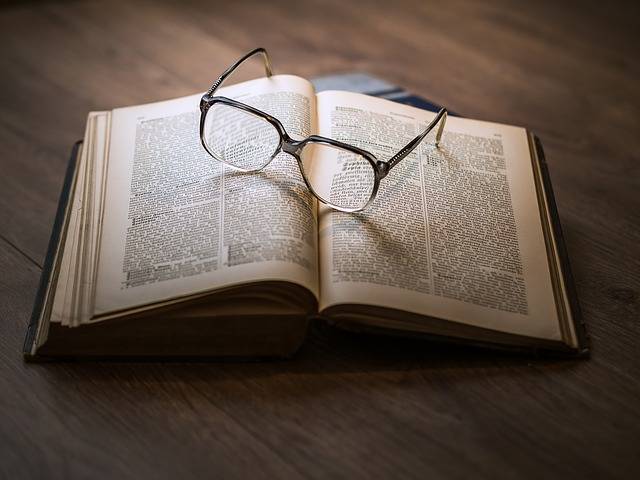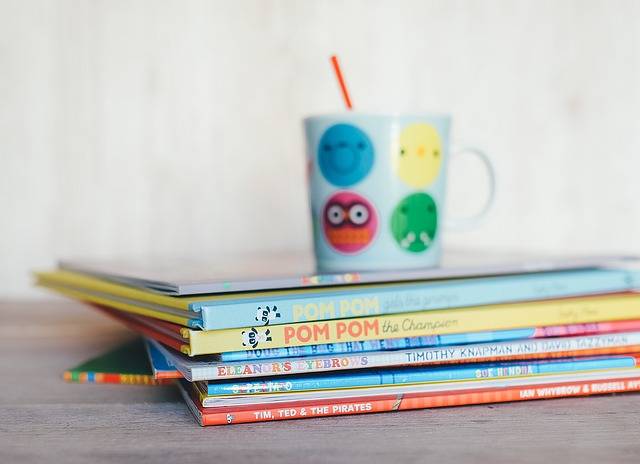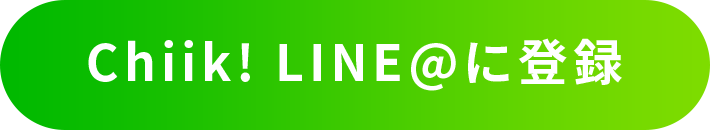2019年09月12日 公開
オルタナティブスクールは学校の新しい選択肢!特徴やメリットを解説
オルタナティブスクールは、進路を決める際の選択肢のひとつです。一般的な学校とどのような違いがあるのかご存じでしょうか?子どもの個性に沿った教育を受けられるオルタナティブスクールの特徴や、通うことのメリット・デメリットなどをご紹介します。
オルタナティブスクールは、進路を決める際の選択肢のひとつです。一般的な学校とどのような違いがあるのかご存じでしょうか?子どもの個性に沿った教育を受けられるオルタナティブスクールの特徴や、通うことのメリット・デメリットなどをご紹介します。
オルタナティブ教育とは?
オルタナティブ教育と言う言葉をご存じでしょうか?「alternative」とは「選択肢」を意味する英語で、慣習的方法をとらない、代わりとなる、型にはまらないなどと訳されることもあります。
現在の公教育とはまた異なる、もっと自由に子どもたちが自分で興味を持ったことを学び進めることや、子どもそれぞれの個性に応じた、個を尊重した教育をしようというものが「オルタナティブ教育」です。生徒すべてに画一的な教育を行うのではなく、子ども自身が課題を見つけて取り組み、それぞれに応じた教育を行うことだと言えるでしょう。
オルタナティブスクールとはどんな学校?
オルタナティブスクール(Alternative school)は、日本ではまだ数が少なく、認知度が低い状況にあります。学校それぞれの教育理念や学習計画に乗っ取った、独自の教育方法で教育が進められるのがオルタナティブスクールの大きな特徴です。
日本で普通にある公立校は、文科省が定めた学習指導要領に沿った教育が行われる認可校ですが、オルタナティブスクールではそのような決まりはありません。必然的にオルタナティブスクールは法的には無認可の学校という扱いになり、多くはNPO法人や一般社団法人が運営しています。
オルタナティブスクールの種類と特徴
独自の教育理念を持つオルタナティブスクールは、方針ごとに違った特徴があります。代表的なオルタナティブスクールをご紹介します。入学を検討している方は参考にしてみてください。
シュタイナー教育
ルドルフ・シュタイナーがドイツでスタートさせた教育実践です。教育そのものが芸術であるとし、このことからも分かるように芸術的分野に力を入れています。
子どもの体と心の発達観に基づき、初等部(小学校)・中学校・高校の12年間の体型的なカリキュラムを組んでいることが特徴です。入学からの8年間は同じ先生が担当し、エポック授業など芸術的な授業が行われます。
モンテッソーリ教育
マリア・モンテッソーリ博士が考案した教育法がモンテッソーリ教育です。子どもの興味や発達段階を大人が正しく理解し、子どもが自主性をもって取り組む環境を整えることが大切だとしています。日本では乳幼児期の教育として取り入れられることが多いモンテッソーリ教育ですが、アメリカやヨーロッパでは大学まで整備されているケースも珍しくありません。
サドベリースクール(デモクラティックスクール)
サドベリースクール、またはデモクラティックスクールと呼ばれるオルタナティブスクールは、特に多くの面で自由度が高いのが特徴です。カリキュラムやテストがなく、学校の運営はスタッフと子どもを合わせたミーティングで決定。毎日の学びは子どもが自分で自由に決めて、自発的に行います。
なお認可制ではなく、サドベリースクールの先駆的存在である、アメリカのサドベリー・バレー・スクールの教育方針に共感した学校の総称です。このため学校によってそれぞれ雰囲気や理念の違いがあります。
サマーヒル
イギリスでA・S・ニイルが創立したサマーヒル・スクールや、哲学者J・デューイの考えをもとに、学校法人きのくに子どもの村学園によって設立されたのが、日本のサマーヒルです。プロジェクトと呼ばれる体験型学習を中心とした学校で、学校法人として認可されています。
イエナプラン
イエナプランはドイツ・イエナ大学のペーターゼン教授が始めた学校教育で、年齢の異なる子どもたちで学級が編成され、対話や遊び、学習、行事などを通した学習活動が行われます。2019年に長野県に全国初のイエナプラン教育私立小学校が誕生することでも注目を集めています。
フレネ教育
フレネ教育は、セレスタン・フレネの教育学に基づいたもので、部分的に取り入れている幼稚園なども多くあります。子どもたちが自分の体験を自由作文に書き起こし、それを教科書の代わりに使用するほか、自由研究の発表と討論などを実施。表現することとコミュニケーションの組み合わせを重視した教育法です。
オルタナティブ教育のメリット
一般公立校とは異なる教育であるオルタナティブ教育。スクールに通うことで得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
子どもが主体性のある学びができる
オルタナティブ教育は、国から定められた教育を受けるというのではなく、自分の「好き」「やりたい」という気持ちを尊重した学びを進めていきます。そのため、子どもが主体性のある学習を進められるように支援しているのが一般的です。公立校よりも体験型学習が多く取り入れられる傾向にあります。
個性が尊重される
子どもの自由な意思決定が重要な教育であるため、現場では子どもの個性を尊重し、伸ばすことが重視されています。少人数制であることが多く、一人ひとりの性質が尊重されやすい環境にあると言い替えることもできそうです。子どもを個性豊かに育てたいときには大きなポイントになるでしょう。
オルタナティブ教育のデメリット
オルタナティブスクールに通うことを検討している場合は、上記でご紹介したメリットとともに、デメリットも事前に知っておく必要があります。
無認可の場合は不登校扱いになることがある
一部私立校として認められたオルタナティブスクール以外は無認可であるため、法的には不登校の扱いになります。ただし自治体によっては、要件を満たした場合に出席扱いが受けられ、小学校や中学校の卒業資格が得られる可能性も。事前に地元公立校の学校長とよく話し合いをしておくことをおすすめします。
公立校に比べて費用が高い
公立校は公的な支援があるため、学費用は抑えられています。オルタナティブスクールの場合、現在は公的な援助が受けられず、費用が高額になりがちです。
学校数が少ない
学校数が少なく、通わせたいと思っても通学できる範囲にオルタナティブスクールがないというのもよくある話です。幼稚園・小学校のみというケースや、小学校・中学校のみというケースも多く、高校で一条校(一般的な学校の意。学校教育法の第1条に掲げられている教育施設)に入学した際に、学校生活や勉強スタイルなどのギャップにとまどうことが予想されます。
フリースクールとの違いは?
本来オルタナティブスクールといえば、フリースクールやホームスクールなどを総称したものですが、現在の日本ではまだそのように認知されているとは言えません。
日本では一般的にフリースクールといえば、不登校になった生徒や一般クラスになじめずに悩む生徒が通う学校というイメージが強いものです。一方のオルタナティブスクールは、一般的な学校教育ではない教育方針や授業の進め方、教育理念などに惹かれて、生徒が自ら入学するという点で異なるものとされています。
どんな理由でオルタナティブスクールを選ぶ?
オルタナティブスクールは、1年生のときから入学する場合もあれば、一条校から転入する場合もあります。親が子どもに「個性を尊重した教育を受けさせたい」と考える場合や、子どもの個性が強く「決められたルールのなかで生活するのが合わない」という場合、何らかの理由で子どもが不登校になり、自由でのびやかな校風に惹かれて入学を希望するなどが多く聞かれる理由です。
公立校とオルタナティブスクールのどちらが正しく、またどちらが間違っているということはありません。子どもが通う学校の選択肢のひとつとして捉えることが大切です。
興味を持ったらまずは見学に行ってみよう
オルタナティブスクールは全国にそれほどたくさんあるわけではありません。通える範囲に学校がある場合や、通っている学校と合わないと感じるときなど、興味をもったらまずは問い合わせ、見学に行ってみましょう。教育理念や子どもの性格のバランス、メリットデメリットなどを総合的に判断することをおすすめします。
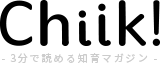

 コバヤシ トモコ
コバヤシ トモコ