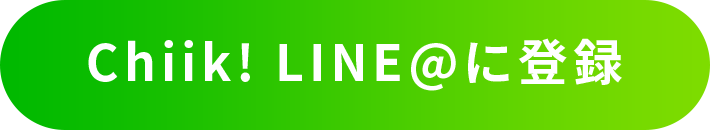この記事では離島での暮らしを、子育ての視点から紹介します。3人の子どもを連れて神奈川から竹富島へ移住しました。自然豊かな中でのびのびと楽しく過ごす子どもたちの様子や、そこからの感じたことや気づきをお伝えします。
竹富島ってどんなところ?
竹富島は観光で人気な島のため、ご存知の方も多いかもしれません。石垣島から南へ6キロ離れた場所にあり、赤瓦の屋根、白砂の道、水牛者など「昔の沖縄らしさ」が島の随所に残っています。
島の集落は国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されていて、昔ながらの集落では古くからの伝統行事が重んじられています。スーパーやコンビニ、信号もなく、のどかで美しい景色が広がる島です。
移住前の子どもたちの反応
私たちが移住した理由は夫の転勤によるものでした。夫から「竹富島への異動希望を出そうと思っている」と相談されたときは驚きましたが「新しい暮らしへのワクワク感」の方が大きかったことを覚えています。
わが家には現在、長男(10歳)、次男(8歳)、長女(4歳)の3人の子どもがいます。子ども達たちを自然に恵まれた環境のなかで育てたいという思いはあったものの、島での暮らしは想像がつきませんでした。転勤が決まってからも、竹富島と石垣島のどちらに暮らすかでしばらく悩みました。石垣島は人口が5万人ほどいて、お店など生活に必要なものがひと通り揃っているためです。
引越す前に一度下見に行ったときは冬で、海に入るのは難しい時期。それでも竹富島のビーチに行くと、子どもたちはこれまでにないほど生き生きと遊びはじめました。砂浜で山を作り、足を埋め、カニや魚を眺め、波と戦い、3時間は夢中で過ごしていたと思います。おもちゃや遊具がなくても遊び続ける姿に私は感激しました。子どもたちも「このままここにいたい~」「たけとみに住みたい!」とすっかり気に入った様子でした。
学校も見学したところ、一面芝生の校庭や花であふれていて、公立の学校とは思えない物語の中に出てくるような空間でした。親子で感激していると、在校生が私たちに「名前なんていうの?」「◯◯と◯◯だね。覚えた!」と親しげに話しかけてくれたのです。
素直で明るい姿に感激していると、子どもたちも「ここがいい!」と目をキラキラさせ、「早く通いたい!」とその気になっていました。子どもたちの熱意に押されて、竹富島で暮らすことを決めました。
年齢に関係なく思い切り遊べる環境
引越した日に近所の方々に挨拶をしました。わが家の子どもたちは恐竜や図鑑が大好きな子や、おままごとが大好きな子たちと意気投合。「明日一緒に遊ぼう!」と、早速翌日家に遊びに来てくれました。
「春休みが終わったら一緒に学校行こうね」「井戸のところで待ち合わせね」引越しの片付けをする横でそんな会話が聞こえます。子どもたちの距離の縮まるスピードには驚くばかりでした。
年齢差も関係なく、2歳から6年生までかくれんぼをしている場面などをよく見かけます。自然と年上の子は小さい子たちに「ほら!こっちに隠れるよ~」とフォローしています。他にも小さい子がトラブルになっていると「そんな言い方はやめなよ」と大きい子が諭している場面もありました。
大人が介入することなく子どもたちのコミュニティ内で解決する様子に感心しています。きっと今はしっかり者の子たちも、小さい頃に同じようにしてもらっていたのでしょう。
地域の温かい目
歴史や文化があり、伝統行事を大切にしている土地。ですから、「他の地域から来たわが子たちがどう迎えられるのだろう」という心配がなかったわけではありません。ところが島には「子どもは宝」という考えが根付いていて、温かい目で見守っていただけています。
ご近所の方に「お兄ちゃん自転車で走ってたね~」「朝早くここの前走ってるよ~」などと話しかけてもらうと安心します。放課後や休みの日も自由にお互いの家を行き来したり、校庭に集まったりしてのびのびと遊んでいます。
はじめの頃は気づくと色々なお友達が家にいることに戸惑いもありました。周りのお母さんたちから「だめなときは言ってね~」「無理しなくていいからね!」と言っていただいたものの、私は「人にはっきり自分の意見を言う」ことに苦手意識がありました。それでも少しずつ意志を伝えられるようになってきて、私も島の暮らしのなかで少しずつ成長しているのかもしれない、と感じています。
「ないなら作る」気持ちが少しずつ
島にはスーパーやドラッグストア、コンビニはありません。小さな商店はありますが、必要な生活用品は船で隣の石垣島へわたって購入します。離島ということもあり輸送費がかかるのか、思った以上に物価が高く驚きました。
以前はコンビニやケーキ屋でスイーツを購入することが好きでしたが、すぐに買いに行くことが難しいためお菓子を作ることが増えました。普段の料理は気が向いたときにしか参加しない子どもたちも、「お菓子作るよ~」と声をかけると「やるやる~」と集まってきます。
また、梅シロップや味噌作りにもチャレンジ。色々なものがない島に来たことで、興味はあったもののこれまでなかなか手を出せずにいたことに挑戦できるようになりました。
自然環境の素晴らしさと大変さ
島で暮らしていると、豊かな自然を身近に感じます。くちばしまで真っ赤なかわいらしいアカショウビン(カワセミの仲間)が学校の体育館に迷い込んだり、オオゴマダラという蝶々の「黄金色のサナギ」が校庭で見られたりしたこともありました。
ある日の散歩からの帰り道、娘が「ジュースを買ってほしい!」と泣きさけんだことがありました。なだめながらようやく家に着くと、なんと目の前に天然記念物の「セマルハコガメ」が!これを見て娘はぴたっと泣き止み、お兄ちゃんたちも呼んで、みんなでしばらくカメがただ動く様子を眺めていました。とても良い思い出です。
虫にはまだ少し慣れないけれど…
自然に囲まれ、家の中に虫やヤモリがしょっちゅう入ってくるため、私は虫刺されの皮膚トラブルに少し悩まされています。庭や道でムカデやサソリ、ハブを見かけたという話も聞きます…!
引越し前は「家の中に小さなクモ一匹でもいるのはちょっと…」という気持ちでした。しかし、今は多少の生き物なら気にならないようになってきました。島での暮らしは夜になると満点の星空が広がり、鳥や虫の鳴き声が響きます。蛍が部屋の中に舞い込んでくることもありました。耳を澄まして目をつぶると、私たちの方が生き物の暮らしている場所に入らせてもらっているように感じます。
とはいえ、生き物に対しては子どもたちがどんどんたくましくなってくれて、日々助けられている母です。
島の暮らしを楽しんでいます
不便なことや大変なこともありますが、豊かな自然の中でのびのび過ごせる子ども時代はかけがえのないものだと感じています。
私の好きな本に、レイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』があります。海洋生物学者であったレイチェルによると、「センス・オブ・ワンダー」とは「神秘や不思議さに目を見はる感性」のこと。レイチェルは自然の美しさを感じる心を忘れてほしくないと言います。作中に次のように書かれています。
美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知のものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。
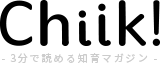

 片岡由衣
片岡由衣