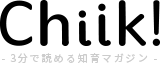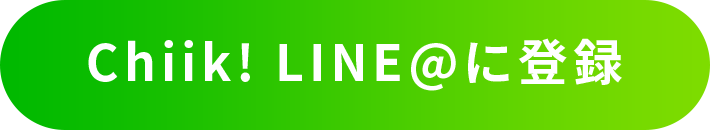子どもから大人まで、人数も関係なく遊べるカードゲームといえば「UNO」。数字と簡単なルールがわかるようになったら、おうち遊びにUNOを取り入れて親子の時間を楽しみましょう。ここではUNOの基本的なルールと、幼児との遊び方をご紹介します。
UNOとは
トランプに次ぐ定番カードゲームといっても過言ではない「UNO」。配られたカードを減らしていき、最初にすべてのカードを手放した人が勝ちというシンプルな遊びです。
このゲームのもととなったのは、「クレイジーエイト」というトランプゲーム。「アメリカンページワン」というトランプゲームにも似ています。これらを専用のカードを使って遊ぶのがUNOといってよいでしょう。
ちなみに「UNO」という名前は、イタリア語で数字の1を意味する「ウーノ」が由来となっています。
UNOが誕生したのは1971年、アメリカで理髪店を運営するマール・ロビンス氏が考案しました。マール氏がこのゲームを周囲の人に紹介すると、これが大好評!そこで家族とともにこのゲームを販売することにしたのです。
現在UNOは、バービー人形の販売で有名な「マテル社」にて販売され、現在にいたるまで世界中で多くの人に愛され続けています。
UNOの基本的なルールと遊び方
UNOはプレイ人数も2~10人までと幅広いうえ、さまざまなアレンジを加えて遊ぶことができるのが特徴。さまざまなローカルルールを加えて遊ぶのも醍醐味ですね。ここではまず、UNOの基本ルールを確認しておきましょう。
1.まずは親を決め、親がカードをシャッフルします。1人7枚ずつ手札を配ったら残りを山にし、山から1枚めくって場におきます。
2.手番は親から時計回り。自分の番が来たら、捨て札の山の一番上にあるカードと色・数字・記号のどれかが同じカードを、手札から出していきましょう。出せるカードがないときは山からもう1枚引きます。
3.数字以外のカードには次の人を飛ばす「スキップ」や、逆回りになる「リバース」などがあります。これらをうまく使いながら、手持ちのカードを減らしていきましょう。
4.手持ちのカードが1枚になったら「ウノ!」の宣言を忘れずに。宣言を忘れてしまった場合は、ペナルティーとして山札から2枚引かなければならなくなります。
5.1~4を繰り返し、最初に全部のカードが無くなった人の勝ちです。
カードの種類
UNOのカードには数字カードのほか、プレイヤーにさまざまな指示を与える記号カードがあります。この記号カードを効果的に使うことが、勝利へのポイントとなります。
・ドロー2(8枚)
このカードを出した人の次の人は、カードの山から2枚引くことになり、自分のカードを出すことはできません。
・スキップ(8枚)
このカードを出した人の次の人は順番を飛ばされます。
・リバースカード(8枚)
順番が逆回りになります。
・ワイルド(4枚)
このカードを出した人は、次の人のカードの色(赤・青・黄・緑)を決めることができます。
・ワイルドドロー4(4枚)
このカードを出した人の次の人は、カードの山から4枚引くことになり、自分のカードを出すことはできません。さらに、次の人のカードの色を任意で指定できます。
ちなみにこのカードの決まりを見てもわかるように、ローカルルールによくあるドロー2返しやドロー4返しなどは、公式のルールではNGなのだそう。ただ、「公式ルールは公式ルールとして、今後も好きなようにアレンジを加えて楽しんでほしい」ともマテル社は述べています。
UNOはいつから遊べる?
UNOをプレイするためには、数字や色がわかること、簡単なルールを理解し守れるようになることが必要です。複雑な展開になると手助けが必要となるかもしれませんが、これらを理解できれば楽しくゲームに参加できるでしょう。
通常のUNOはまだ難しいと感じる3歳頃は、カードをキャラクターで分けて種類を減らした「はじめてのウノ」などを利用すると、とっつきやすいかもしれません。
5歳頃から少しずつ記号カードの効果的な使い方を理解できるようになり、作戦も自分で練ることができるようになってきます。ここまでできると、通常のUNOを大人と一緒に楽しむこともできるでしょう。お子さまの年齢やレベルに合わせた遊び方を工夫し、チャレンジしてみてください。
幼児とのUNOの遊び方のコツ
小さなお子さまを交えて家族みんなでUNOを楽しむには、子どもに合わせた遊び方の工夫が必要になります。簡単な遊び方からスタートし、子どもの理解度に合わせてレベルアップさせていきましょう。
幼児とUNOを行うとき、具体的にどういったことに気をつけるとよいのかご紹介します。
色や数のヒントを
次に出せる色や数のヒントを教えてあげると、小さなお子さまでも参加しやすくなります。「赤のカードか3のカードがあれば出せるよ」など、出せるカードの選択肢を教えてあげることがポイントです。
記号のカードは使わず、数字のみのカードを使って遊んでみるのもいいかもしれません。スキップやドロー2など、記号カードの理解には時間がかかりますが、色と数だけなら3歳位から楽しめます。
カードをオープンに
子どもの遊びへの興味と学びには、目を見張るものがあります。同じ数・同じ色のカードを順番に出していくルールはあっという間に覚えてしまうでしょう。難しいのは記号カードの扱いです。
そこで、記号カードの意味を理解できるまではカードをオープンにし、出すタイミングを教えてあげてください。そうすることで自分が出したカードで次の展開が変わる面白さに気づき、さらにゲームを楽しむことができるでしょう。
UNOで家族の時間を楽しもう
UNOをはじめとしたカードゲームは理解力、思考力、忍耐力を養うことができます。何より楽しい家族団らんの時間が、子どもの健やかな成長にいい影響を与えることは言うまでもありません。自分でできる楽しさを知るほどに「もう1回!」の声が止まらなくなるでしょう。
お子さまのレベルに合わせた遊び方から少しずつ難易度をあげ、家族でUNOを楽しんでくださいね。
▼スタンダードなものからキャラクターまで魅力的な商品がいっぱい🎶